これから、二期会で7月に上演されるベルク作曲「ルル」について何度かに分けて書いていきたいと思う。
まずは「ルル」の原作である戯曲「地霊」と「パンドラの箱」を書いた劇作家、フランク・ヴェーデキント(1864〜1918) と、彼が生きていた社会について。
「ルル」は、戯曲や小説を原作としたオペラの中では原作をかなり忠実になぞった作品と言えるので、原作と原作者についてよく知っておくことは不可欠である。
ヴェーデキントは私にとっては何よりも「春のめざめ」の作家である。
「春のめざめ」はヴェーデキントの初期の戯曲で、思春期の性への目覚めと、19世紀後半ヨーロッパの抑圧的な社会の矛盾を描いた作品。今読んでも斬新でスリリングな戯曲だ。劇中には性描写のみならずSMや同性愛も描かれており、当時の作品としてはテーマ的にも、スタイル的にもタブーだらけで、検閲で上演禁止となり、1891年に出版されてから上演されるまでに15年もかかった。
ギムナジウムに通う14歳の男子メルヒオールとその友人たちは、暗記ばかりのつまらない勉強や道徳観念を押し付けられる学校と、欺瞞に満ちた教師たちや大人たちにうんざりしている。大人たちは「正しいこと」ばかりを口にするが、本当のことは誰も教えてくれず、悩みを相談しても自分の保身に走るばかり。彼らは「男の衝動」について自分たちの限られた知識を教えあう。一方、同い年の女子ヴェンドラは自分の体の変化に戸惑っているが、母親に妊娠や出産の仕組みについて聞いてもごまかされてしまう。メルヒオールとヴェンドラは正しい知識がないままに仲良くなり、ヴェンドラは妊娠した挙句、中絶が失敗して死んでしまう。
ヴェーデキントは、この作品のエピソードはほとんどどれも、自分の学校時代の体験に基づいていると言っている。
「春のめざめ」は2006年にブロードウェイでミュージカル化されて(Spring Awakening)、トニー賞作品賞を受賞するなど大ヒットした。
これがとにかく、音楽も詩も演出もめちゃくちゃかっこいいロックミュージカルなのだ。
まずはトニー賞でのパフォーマンスの映像。3分程度なのでぜひ見てみてください。
https://www.youtube.com/watch?v=L_Bl9NIBvY8
ミュージカルの設定は原作通りの19世紀後半なのだが、10代の男女のエネルギーやフラストレーションをロックで表現している。人物たちは内面を表現する際、舞台前に出てきて、ハンドマイクを持ってロックコンサートのように歌う。ヴェーデキントの尖った感性を、演出も含め、現代の感性に置き換えて蘇らせている。
楽曲も最高だが、スティーブン・セイターによる歌詞が、比喩とイメージに満ちていてとんでもなく素晴らしい。世界中の古典から引用したりしていて、歌詞というよりは良質な詩であり、他の言語で訳詞を作るのはほとんど不可能と思わせる。劇団四季版の日本語訳詞も成功していたとはいえない。
演出はマイケル・メイヤーで、最近はオペラも手掛けており、2018年に新制作されたMetの現在の「椿姫」はメイヤーの演出である。
10代のヌードやセックスシーンで話題になったが、そんなことよりも、この楽曲と詩と世界観はスマートで洗練されていて、近年のミュージカルの中では最高傑作の一つだと思う。
実は私はこのミュージカルが劇団四季で上演された際、稽古場で音楽監督の通訳をさせていただいた。音楽監督のKimberly Brigsbyは非常に情熱的で、音楽が始まると全身に音楽が憑依する、巫女タイプのミュージシャンであった。彼女はブロードウェイで上演中のほとんどの本番を舞台上で指揮しており、トニー賞の映像にも、その憑依した指揮姿が一瞬映っている。
四季版は大ヒットとはならず数ヶ月でクローズしてしまったが、初演で主役のメルヒオールを演じた柿澤勇人君は現在、日本のミュージカル界のスターの一人になっている。彼も憑依タイプの俳優で、当時から、稽古で役に入った時の集中力は眼を見張るものがあった。
さて、ミュージカルの元となっているヴェーデキントの戯曲「春のめざめ」と、作家本人の話に戻る。
ヴェーデキントは不条理劇の先駆者と言われており、ブレヒトに多大な影響を与えた。彼の作風は、自然主義の全盛期だった当時の戯曲としては異色である。不自然な誇張があったり、シンボリックであったり。そしてテーマは性や暴力など、当時の社会のタブーに切り込んでいるものが多い。
「春のめざめ」の世界は、シュテファン・ツヴァイクの自伝「昨日の世界」と併せて読むと非常に理解が深まる。
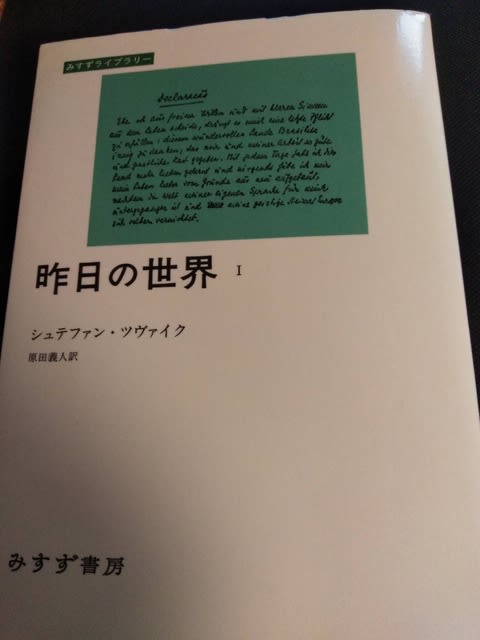
ツヴァイクは19世紀末、「春のめざめ」で描かれたそのままの世界で学校時代を過ごした。
「昨日の世界」によれば、当時のドイツおよびオーストリアの学校での教育は、知識を厳しく詰め込まれるばかりで、無味乾燥で退屈極まりなく、人間的な温かみは一切なかったという。
また、当時の中産階級の道徳は極度に抑圧的で不健康だった。生活の中で性についての話題は巧妙に避けられ、あたかも人間社会に性が存在しないかのようで、特に女性は結婚するまで一切性について知識を得ることもタブーだった。若い男女の健康的な付き合いというものは存在しなかった。その分、売春がはびこり、男性は性病への怯えを常に抱えていた。そういう矛盾に満ちた社会だったのだ。
授業は味気なく退屈だったが、当時のウィーンの学生たちは学校とは無縁なところで、新しい芸術を発見することに夢中だった。時はまさに世紀末芸術、ユーゲントシュテルの時代で、美術でも音楽でも文学でも、それまでの価値観を担うロマン派とは違う、革新的な表現が次々と生まれていた。ツヴァイクと仲間たちは、早くからリヒャルト・シュトラウス、ドビュッシー、シェーンベルクの音楽、リルケの詩、ストリンドベリの戯曲、ムンクの絵画などに熱中し、彼らより少し年が上で、若くして颯爽と文壇デビューしていたホフマンスタールに憧れた。
「われわれは、いわば風が国境をこえてやって来ないうちに、それを嗅ぎつけた。・・・われわれの世代は、われわれの教師たちや大学が知らないうちに、芸術においても古い世紀とともに何事かが終わったのであり、革命が、少なくとも価値の転換が緒につき始めているのだ、ということを感じていたのであった。」(「昨日の世界」)
ヴェーデキントはまさに、そういった新しいアーティストの一人であり、ツヴァイクや仲間たちにとってはアイドル的な存在だったのである。「例えばヴェデキントの上演や新しい抒情詩の朗読のような、一つの実験が試みられるところには、われわれは間違いなく、ただわれわれの魂ばかりでなく、われわれの手の全力を挙げて、馳せ参じた。」(「昨日の世界」)
「昨日の世界」には「春のめざめ」という一章があり、当時の性にまつわる風習と価値観を批判的に書いている。これはヴェーデキントに捧げた章に違いない。
そして、この先端的な若者たちの中に、ベルクもいた。1905年、ウィーンでルルの原作戯曲「パンドラの箱」が上演された際、ベルクも観客席に座っていたのである。

